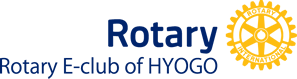第499回例会
Rotary E-club of HYOGO
2025年5月26日開会
5月は青少年奉仕月間です。
はじめの点鐘
ロータリーソング
SAA: 今週のロータリーソングは、「R-O-T-A-R-Y」です。元気よく歌いましょう。
-
♪ R-O-T-A-R-YOpen or Close
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y
Is known on land and sea;
From North to South,from East to West;
He profits most who serves the best;
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y
Is one great family;
Where friend-ship binds for man’s up-lift.
Where each one strives his best to give,
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.
会長の時間
皆さんこんにちは!
先日勤務校の生徒研修の事前調査のために「兵庫津ミュージアム」に行きましが、こちらが大変多くの学びがある素晴らしい施設でしたので、少しご紹介したいと思います。
「兵庫津(ひょうごのつ)」というのは神戸市兵庫区の南側にあった港で、現在は神戸港西側の一部となっています。兵庫津は、古くから重要な航路であった瀬戸内海に位置し、六甲山系によって北西の季節風が遮られるとともに、西からの荒い波は和田岬によって防がれ、さらに水深やラグーンにも恵まれた天然の良港でした。
かつては「大輪田泊(おおわだのとまり)」と呼ばれ、行基により築かれたとされています。近畿から中国・九州へ向かう航路の船泊りとして機能し、804年には、第4回遣唐使の一員として最澄や空海らが船出していきました。平安時代の終わりごろには、平清盛が日宋貿易に大輪田泊を利用し、大きな港に大修築して重要な国際貿易港になりました。
鎌倉時代以降になると兵庫津と呼ばれるようになり、室町時代には、勘合貿易の国際港として栄えます。江戸時代には宿場町として、また天下の台所・大坂の外港として、さらには北海道、東北の日本海沿岸と近畿を結ぶ北前船の発着港として大きく発展し、人口も5~6千人ほどから江戸中期には2万人を超える大都市となります。
1826年に兵庫を訪れたシーボルトは「港内には絶えず非常に多くの大小の船舶が停泊し、郊外には数えきれないほどの船が大坂に向っていくのが見える」と記し、「世界中探しても、ここほど船が往来している水域はない」との感想を残しています。
幕末に幕府が締結した日米修好通商条約を初めとする欧米との通商条約では、横浜、新潟、函館、長崎と共に兵庫を外国船に開港することが規定され、大政奉還後は明治新政府により、兵庫県の最初の県庁が兵庫城跡に置かれて初代県知事に伊藤博文が就任しました。
兵庫の開港は1868年ですが、実際に欧米諸国に開放されたのは兵庫津ではなく神戸村でした。欧米諸国が付近の海域を測量した結果、兵庫津より神戸の入り江の方が大水深で、より大きな船の受け入れには適していると判断し、さらにその後方に広がる未開発の土地が居留地に選定されたのです。神戸村が開港したこともあり、徐々に貿易港としての役割は新しい神戸港に譲っていきましたが、兵庫津が現在の神戸、引いては兵庫県発展の礎となったことは間違いありません。
「兵庫津ミュージアム」は、このような歴史を、映像や豊富な資料などで楽しみながら学べる施設となっています。また初代兵庫県庁となった建物を復元し、見学できるようにもなっています。わが地区の成り立ちを考えるうえでも、大変すばらしい施設です。近くには、神戸中央市場や兵庫大仏、和田神社そして矢坂誠徳ガバナーが住職をお勤めの瑞龍寺もございます。近隣にお立ち寄りの際は是非ご訪問いただければと思います。
幹事報告
第52回神戸まつり おまつりパレードご参加御礼
拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素はロータリー活動に
ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先日開催されました第 52 回神戸まつりおまつりパレードにおきまして、
多くの方々にお集まりいただき、誠にありがとうございました。また、クラブ内で
のお声かけを賜り、皆様のご協力に心より感謝申し上げます。
また、今後地区にて開催する際にも、お力添えをいただけますと大変ありがたく
存じます。
改めまして、この度は誠にありがとうございました。
国際ロータリー第2680地区
ガ バ ナ ー 矢坂 誠徳
ロータリー財団委員長 吉岡 博忠
ポリオプラス小委員長 榊 誠
卓 話
英語をめぐることばの旅
HYOGO ロータリーEクラブ会員 傅 建良
本日は、英語にまつわる雑学をテーマに、日頃の学習や会話ではあまり触れることのない、しかしどこかで気になったことのある、ことばをめぐる話題を三つほどご紹介したいと思います。
1. なぜ “I” は常に大文字で書くのか?
現代英語の一人称代名詞単数形 I は、ich やı の形態を経て、現在の形に定着しています。小文字書きが基本であった中世では、一人称代名詞単数のı は、縦棒で表記するn (= ıı)やm (= ııı)と紛らわしいという問題が生じました。その問題を解消するために、点をつけたi を使用したり、代用としてy を用いたりする回避策が取られました。しかし、結果的に大文字のI が標準的な表記として定着しました。
2. 「China」ということばの由来は?
“China”は、古代中国を統一した「秦(Qin)王朝に起源を持ちます。紀元前221年に中国を統一した秦の名は、西方の遊牧民族である匈奴(Xiongnu)などを経由して、ペルシャ語やサンスクリット語で「Cin」や「Chin」と呼ばれるようになりました。その後、この呼称がヨーロッパに伝わり、ラテン語的な語尾変化「-a」が加わることで、China という名称が定着しました。この例は、言語と歴史、さらには国際交流がどのようにして現在の語彙を形作ってきたのかを示す、興味深い証左のひとつです。
3. IKEA は「イケア」で通じない?
日本でも高い人気を誇るスウェーデン発の家具量販店 IKEAについて、日本語では「イケア」と発音されることが一般的ですが、これはスウェーデン語の原音([ɪˈkɛa])に近いものです。一方、英語圏では IKEA を「アイキーア」 /aɪˈkiːə/ と発音するのが一般的です。したがって、英語話者との会話では、日本式の「イケア」では伝わりにくい場面も生じます。これは、グローバルブランドのローカル化がもたらす興味深い一例であり、同時に「発音の多様性」に対する理解の必要性も示しています。
おわりの点鐘
この例会に共感された方は、「いいね」をお願い致します。