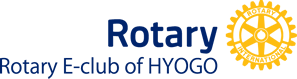日本のアフガニスタン避難民が抱える問題
アフガニスタンの首都カブールが陥落し、タリバンが実権を掌握してからはや1年半。

元はというと、2001年9月11日にアメリカで起きた同時多発テロを契機に始まったアフガニスタン紛争がきっかけとなっており、それが日本を含む西側諸国の「自由と民主主義」という正義を守る闘いへと発展。タリバン政権打倒後にアメリカ・NATO軍が駐留を続けながら、この国を二度とテロリストの温床にしないための国づくりが行われていました。
日本はアフガニスタン復興支援として、祖国の将来を担う若者への教育支援を行い、日本政府国費による留学や国際協力機構(JICA)の協力で数多くのアフガニスタン人が日本の大学で学びました。以来、日本へのアフガニスタン人留学生の数は、20年間で約1400人にのぼります。
しかし、タリバンが再び政権を掌握した2021年8月以降、民主主義国である日本につながりがあることや、アフガニスタン旧政府で働いていたことを理由に元留学生たちが脅迫や迫害を受け、自身と家族の安全を確保するために日本に避難し始めました。
ただ、そこには大きな壁があります。日本政府はウクライナ避難民への対応は行っているものの、ほかの国については基本的に移民は受け入れていないため、アフガニスタン避難民が日本に住める期間は1年間だけなのです。受け入れ現場での具体的なサポートは民間団体やNGOが受け持つ形になっていますが、避難一年間で日本語を習得させ日本での就職先を見つけられなければ、結局はアフガニスタンに還されて命の危険にさらされることになります。宮崎大学の先生方も救済を開始し、その中に私たち宮崎アカデミーロータリークラブの会員がいました。
宮崎に避難しているアフガニスタン元留学生は、当時のことをこう言います。「みんな理由もなく殺された。誰がどんな理由で殺されたのかが分からないほど状況は深刻だった。とても怖かった。私も殺されるかも知れないと思って、国を脱出しようと決断した」
アフガニスタン人道支援コロキュームを開催
そのようなアフガニスタン避難民のために少しでも何かできることはないかと思い、私たちのクラブは、神戸在住のアフガニスタン人アーメッド氏をお呼びしての基調講演、そして元留学生ご家族から直接お話を聞きながらのパネル討論というコロキュームを開催しました。

また、学生ボランティアの「アフガニスタン人に日本語を話そう会」の活動報告もしてもらいました。現在、アフガニスタン人のお子さんたちが大学の近くの小学校に通えるようになり、今ではかなり日本語が上手になってきたとの報告を受けています。
さらに、アフガニスタンの文化交流としての展示や、食文化の交流としてハラル*認証カレー弁当を販売しました。一般市民にこのハラル認証の存在と味を知ってもらえたことは、大きな意義があったと思います。カレー弁当の収益はすべて、宮崎大学のアフガニスタン人道支援へ寄付しました。
次年度もこのアフガニスタン人道支援コロキュームの開催を計画しています。次回は地区補助金を利用する計画を立て、現在申請中です。
ところで、宮崎ウクライナ避難民支援ネットワーク会長であり元宮崎国際大学学長の隈元正行氏が、今回のコロキュームへの参加をきっかけに、この1月、宮崎アカデミーロータリークラブに入会されました。またもう一人、コロキュームに合わせてアフガニスタン文化のパネル展示を担当してくださった宮崎大学の石川千佳子副学長も、同じく1月に入会されました。
コロキュームの元々の目的は避難民人道支援に関する啓発でしたが、文化交流や学生ボランティアによるアフガニスタン支援活動、マスコミの取材によるアフガニスタン避難民の存在に対する認知向上、さらにはロータリークラブへの入会など、大きな実りがありました。これは、現在の世界で次々と起きている悲惨な暴力に対する人びとの強い危機感の表れであると同時に、ロータリーの活動が地域に理解されれば、自然と認められ、協力者も得られるということを示していると思います。
継続してこそ人びとの意識が定着します。今後は持続可能な体系を作っていきたいと考えています。
開会時、君が代とアフガニスタン国歌を全員で斉唱したとき、涙をこぼすアフガニスタン元留学生ご家族の姿がありました。最後に、私が感動したアフガニスタン人の言葉をご紹介します:
「タリバン政権は、全国民の一部の人間がやっていることです。すぐには解決しないけれど、必ず国際的に認められる国になっていくので、どうぞアフガニスタンを見捨てないようお願いします」
日本人ロータリアンとして、ここ日本で国境を越えて人を思いやり、大切にする人権意識を喚起することが、世界の平和につながっていくものと信じています。

*ハラル=イスラム教を信仰するムスリムの人びとが食べられるもの。