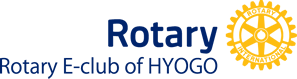第486回例会
Rotary E-club of HYOGO
2025年2月3日開会
2月は平和構築と紛争予防月間です
はじめの点鐘
ロータリーソング
SAA: 今週のロータリーソングは、「君が代」と「R-O-T-A-R-Y」です。元気よく歌いましょう。
-
♪ 君が代Open or Close
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
巌(いわお)となりて
苔(こけ)のむすまで -
♪ R-O-T-A-R-YOpen or Close
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y
Is known on land and sea;
From North to South,from East to West;
He profits most who serves the best;
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y
Is one great family;
Where friend-ship binds for man’s up-lift.
Where each one strives his best to give,
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.
会長の時間
皆さんこんにちは!先週は仲内ガバナー補佐ご臨席の下、宝塚ロータリークラブ、宝塚武庫川ロータリークラブ、そして宝塚ユニバース衛星クラブをお迎えしての合同例会でした。今回あえて通常のEクラブの形式で合同例会を開催しましたので、日頃は対面での例会を行っている皆様にも、当クラブについて理解が深まったのではと思います。
さて、今月は「平和と紛争予防/ 紛争解決月間」です。ロータリーのホームページを見ますと「平和の推進」は7つの重点活動分野の1つと位置付けられ、また「平和な環境をつくるロータリー」と題して「人道的組織として、平和はロータリーの使命の礎となるものです。私たちは、地域社会での平和構築のために人びとが協力すれば、その変化が世界的な影響を生むと信じています」との記述があります。
このように、平和構築にロータリーは力を入れていますが、そもそも「平和とは何か?」とその定義について問われると、案外難しいものです。一般的には平和とは、「国際関係において戦争が発生していない状態」を意味しますが、この意味において有史以来人類が平和であった期間は、累算でもわずか6年程度であるという研究があります。
私は倫理教師の端くれですので、ここでドイツの哲学者カントの思想を紹介したいと思います。カントは『永遠平和のために(Zum Ewigen Frieden)』で平和について論究していますが、この著作はヨーロッパで国家間の紛争が頻発していた1795年に発表されました。この中でカントは、平和を単に戦争がない状態としては捉えておらず、政治的ならびに道徳的な条件が成立してこそ、持続可能で安定した真の平和が実現できると述べています。その平和を実現するための政治的条件とは各国の「戦争放棄」であり、道徳的な条件とは「人に対する敵意のない状況の構築」としています。
カントは、ただ単に戦争がない消極的な平和ではなく、永続的な、いわば積極的な平和の実現の必要性を主張していると言えます。カントは国際平和機構の設立も提唱していましたのが、その後その理念は第一次世界大戦後に国際連盟成立として結実します。
ロータリーは政治的条件である「戦争放棄」には直接には関われませんが、道徳的な条件については、ロータリアン一人ひとりが貢献しうるのではないでしょうか?現にロータリーが行っている「紛争の予防・仲裁や難民支援に当たる人材を育て、異文化間の交流と対話を促すこと」はこの道徳的条件の確立に他ならないのではないと私は思います。
さらには、ロータリーの職業奉仕の推進こそ、畢竟もっとも基礎的な平和への道であるとも私は考えますが、その点につきましては次回に譲りたいと思います。
幹事報告
卓 話
平和と紛争予防 / 紛争解決月間によせて
~平和と紛争予防を考える~
みなさま、元気でお過ごしでしょうか?
表題のテーマを考えるにあたって
「第二次世界大戦後の紛争」を振り返ります。
1. スエズ危機(1956年)
エジプトが「スエズ運河の国有化」を宣言した後、
イギリス、フランス、イスラエルが軍事介入しました。が、
米国とソ連の圧力によりこれらの国々は撤退を余儀なくされました。
2. キューバ危機(1962年)
米ソ冷戦中のキューバ危機は、
「核戦争の瀬戸際」まで進んだ重大な紛争でした。
しかし、ケネディ米国大統領とフルシチョフソ連首相は
直接的な通信を通じて解決策を模索しました。
最終的には、ソ連がキューバから核ミサイルを撤去し、
米国もトルコから同様に撤去するという合意に達しました。
3. フィンランド化(冷戦期)
第二次世界大戦後、
フィンランドはソビエト連邦との間に厳しい平和条約を結びましたが、
その後も独立を保持し続けました。
フィンランドは西側諸国との良好な関係も維持しながら、
ソビエト連邦との緊密な外交関係を構築しました。
この「フィンランド化」と称される政策は、
大国間の緊張が高まる中でも中立的な立場を保ち、
紛争を避ける手法として注目されています。
4. 北アイルランドの和平プロセス(1998年グッドフライデー協定)
北アイルランドの紛争は、
カトリック派とプロテスタント派の
民族的・宗教的対立が根底にありましたが、
1998年のグッドフライデー協定により
暴力的な対立に終止符が打たれました。
この協定は、英国政府、アイルランド政府、
および北アイルランドの主要政党間で行われた
複数年にわたる交渉の成果です。
この事例は、「持続的な対話と政治的妥協」が
紛争解決に欠かせない要素であることを示しています。
5. コソボ紛争の解決(1999年)
コソボ紛争は、
1990年代後半にユーゴスラビア連邦からのコソボの独立
を巡る暴力的な衝突に発展しました。
北大西洋条約機構(NATO)の軍事介入と国際社会の圧力が、
1999年の和平へとつながりました。
この介入は、地域的な安定性を保つための国際的な行動が
どう影響するかを示す事例です。
6. 東ティモールの独立(2002年)
東ティモールは、インドネシアからの独立を巡る暴力的な紛争後、
2002年に正式に独立しました。
国連の安全保障理事会が
国連東ティモール暫定行政機構(UNTAET)を設置し、
平和維持と国家再建のための支援を行ったことが成功の鍵となりました。
7. ケニアの政治危機解決(2008年)
2007年の選挙後に発生した暴力と政治的緊張が、
ケニアを大規模な内戦に陥れる可能性がありました。
しかし、国際社会の仲介により、
2008年には政治的な対立グループ間で和解が成立しました。
この協定には、前国連事務総長の
コフィー・アナンが中心的な役割を果たしました。
8. コロンビア政府とFARCの和平合意(2016年)
コロンビアでは50年以上にわたる内戦が続いていましたが
2016年に政府と革命軍(FARC)が和平合意に至りました。
この和平プロセスには、複数の国々が仲介者として関与し、
特にキューバとノルウェーが重要な役割を果たしました。
9. 南スーダンの独立(2011年)
長年にわたる北スーダンとの内戦の後、
南スーダンは2011年に独立を達成しました。
これは、包括的平和協定(CPA)の結果であり、
国際社会、特にアフリカ連合と国連の支援が重要でした。
10. フィリピンとモロ・イスラム解放戦線(MILF)の和平合意(2014年)
フィリピン政府とモロ・イスラム解放戦線は、
長年にわたる紛争の後、2014年に和平合意に署名しました。
この合意には、ミンダナオ島の自治拡大が含まれており、
MILFの戦闘員の社会への再統合を促すことが期待されています。
11. イラン核合意(2015年)
2015年には、
イランとP5+1(米国、英国、フランス、ロシア、中国、ドイツ)
が核開発プログラムに関する包括的な合意に達しました。
この合意は、イランが核武装を進めることなく、
国際社会との緊張を軽減するためのもので、
経済制裁の解除と技術的な制限の導入を含んでいます。
◆これらを調べていて気になったのは、
「これらの国際紛争が派生した原因を類別すると
どんな項目が何例ずつあるか?」についてです。
各紛争の原因は複数のカテゴリにまたがる場合もありますが、
主要な要因を基に分類してみると…、
1. 民族的・宗教的対立
o 北アイルランドの和平プロセス(1998年グッドフライデー協定)
o コソボ紛争の解決(1999年)
o 南スーダンの独立(2011年)
o フィリピンとモロ・イスラム解放戦線(MILF)の和平合意(2014年)
2. 領土・国有資源の争い
o スエズ危機(1956年)
o 東ティモールの独立(2002年)
3. 政治的・経済的緊張
o ケニアの政治危機解決(2008年)
o コロンビア政府とFARCの和平合意(2016年)
4. 冷戦期の代理戦争および国際的緊張
o キューバ危機(1962年)
o フィンランド化(冷戦期)
5. 核開発と国際的な安全保障
o イラン核合意(2015年)
となります。
これらの分類から、民族的・宗教的対立が4例、
領土・国有資源の争いが2例、
政治的・経済的緊張が2例、
冷戦期の代理戦争および国際的緊張が2例、
核開発と国際的な安全保障が1例という分布になります。
多くの国際的な紛争が
民族や宗教のアイデンティティー、
国家の安全保障、
資源の配分、
などの要因に根ざしていると言えるでしょう。
◆では国際紛争を未然に防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか。
もちろん単純なことではなく、
多様なアプローチが必要なのは明確です。
しかしながら、以下に歴史上有効だった主要な対策を挙げてみます
1. 外交関係の強化
定期的な外交対話を通じて、
国々の間の理解と信頼を深めることが重要です。
外交は、緊張が高まる前に潜在的な問題を解決する
プラットフォームを提供します。
2. 経済的相互依存の促進
経済的な相互依存が高まると、
紛争に走ることのリスクやコストが増加し、平和的な関係が奨励されます。
自由貿易協定や共同投資プロジェクトなどが該当します。
3. 国際法と規範の遵守
国際法や国際的な規範の尊重は、
国際社会における行動の基準を設けます。
国連憲章や各種の国際条約は、
紛争を法的なフレームワーク内で処理するための指針を提供します。
4. 多国間での安全保障協力
地域的な安全保障機構や国際的な平和維持活動への参加が、
潜在的な紛争の抑制に寄与します。
NATOやアフリカ連合の平和維持活動が例として挙げられます。
5. 紛争予防と危機管理の機構
予防外交や危機管理の専門機関を通じて、
緊張がエスカレートする兆候を早期に察知し、
適切な対応を行います。
国連などの国際機関がこの役割を担っています。
6. 教育と文化交流の促進
異文化理解を深める教育プログラムや文化交流は、
国際理解を促進し、
偏見や誤解を減少させる効果があります。
これにより、国隅間の対話がスムーズになります。
7. 地域的な問題に対する国際社会の協力
気候変動や資源の枯渇といった地域的な問題に対して、
国際社会が協力して取り組むことで、
これらが原因で発生する可能性のある紛争を防ぐことができます。
これらの対策を組み合わせて行うことで、
国際紛争の発生リスクを低減し、
より平和な国際関係を築くための基盤を強化することが可能です。
◆平和を維持するためには?
まずは前項の1~7がこれまで実績として有効だったことが参考になります。
ただ、ひとりひとりが出来る事は
「誰もが平和を心底願うこと」
とても重要じゃないでしょうか。
・・紛争や戦争のデメリットや波及リスクなどを理解し
WIN―WINやシナジーの大切さを知る。
そして、平和の価値や重さを心底理解納得する。
↓
そういった意識で実現に向けて、
様々な障壁やコンフリクトを乗り越えられる
しなやかな体制を作る。
↓
実現のため、実行改善を繰りかえす。
これを地球全体レベルでやるのは
もちろん並大抵のことではありません。
…が、個人的には
ジョン・レノンの「イマジン」の世界観が浮かぶのです。
私見ではありますが
私が日本人として更にしっくり来るのは
忌野清志郎さんが日本語訳詞でこの楽曲をカバーされて、
ちょっとだけ歌詞を付け足して歌ったものです。
イマジン (訳詞 忌野清志郎)
天国はない ただ空があるだけ
国境もない ただ地球があるだけ
みんながそう思えば
簡単なことさ
社会主義も 資本主義も
偉い人も 貧しい人も
みんなが同じならば
簡単なことさ
誰かを憎んでも 派閥を作っても
頭の上には ただ空があるだけ
みんながそう思うさ
簡単なこと 言う
夢かもしれない
でもその夢を見てるのは
君ひとりじゃない
夢かもしれない
でも一人じゃない 「ぼくらは薄着で笑っちゃう」
夢かもしれない 「ああ 笑っちゃう」
かもしれない 「ぼくらは薄着で笑っちゃう」
「ああ 笑っちゃう」
「ぼくらは薄着で笑っちゃう」
「ぼくらは薄着で笑っちゃう ああ笑っちゃう」
→これは清志郎さんが勝手に付け足した歌詞ですが、
薄着 = 戦争放棄、もちろん核なんて持たない という解釈説もあって、
笑っちゃう = それでも平気で笑ってるということ
なのか? 自虐なのか?
いずれにしろこの世界観は
安定した世界平和を手に入れるための
カギになりそうだと思います。
忌野清志郎さんの名前を書いていて、
長澤会長エレクトがいつも清志郎さんの曲を歌ってる姿が
ふと思い浮かびました。
ああ、平和やなあ~
渡邊 誠
おわりの点鐘
この例会に共感された方は、「いいね」をお願い致します。