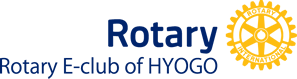第262回例会
Rotary E-club of HYOGO
2020年3月16日開会
3月は水と衛生月間ですは水と衛生月間です
はじめの点鐘
ロータリーソング
SAA: 今週のロータリーソングは、「我らの生業」です。元気よく歌いましょう。
-
♪ 我らの生業Open or Close
一、我等の生業さまざまなれど
集いて図る心は一つ
求むるところは平和親睦
力むるところは向上奉仕
おゝロータリアン 我等の集い
二、奉仕に集える我等は望む
正しき道に果をとるを
人の世挙りて光を浴みつ
力を協せて争忌むを
おゝロータリアン 我等の集い
会長の時間
HYOGOロータリーEクラブ会長の長澤友滋です。
いつもありがとうございます。第262回例会でございます。
世間での話題はコロナ、コロナ・・・でいっぱいなので、あえて今回は別のテーマで。
ソメイヨシノについて。
今、読んでいる本が『午前8時のメッセージ99話~意味ある人をつくるために~』というタイトルで、著者は草柳太蔵さん。きっかけは、先日亡くなられたプロ野球の名監督・野村克也さんがこの草柳さんの本を読んでいた、と目にしたことです。最近は便利な世の中で、すぐAmazonで検索してポチポチしていると本が届く時代です。さっそく読み始めてみました。
その本で『ソメイヨシノ』の話題がありましたので紹介します。
日本人は桜が咲くのを見ると『春が来たなー』『きれいだなー』と明るい気持ちになるものです。
その桜にもいろいろ種類があるわけですが、今の日本の主流が『ソメイヨシノ』だそうです。なぜなら、ソメイヨシノは東京・駒込の植木職人が人工的に作ったクローン桜だから。さらにソメイヨシノは見た目もきれいなので、どんどん全国に広がり、今や世界で桜が鑑賞できる時代ですね。
しかし、人工的である故、弱点もある。それが、育てるのに手間がかかり、手を加え続けると樹が弱くなっていく過保護な桜だそうです。手間をかける理由が、美しい枝ぶりでたくさん花が咲く、という人間の欲望のためであるわけで、考えさせられる話だと思いました。
これは人も一緒。子供や社員教育において、もちろん美しい枝ぶりでたくさん花が咲くように育って欲しいと願うわけですが、それが親や社長の欲望であってはいけませんし、過保護すぎては弱い人になってしまいます。無理やり花を咲かせるのではなく、自ら花を咲かせるサポートをしていきたいものです。
今年は暖冬の影響で桜も早く咲くようです。例年のような花見でどんちゃん♪な空気ではありませんが、ソメイヨシノの話を思い出して、ただ『きれいだなー』だけに終わらない春にしたいと思いました。
では、まだまだウイルスに対して警戒をしつつ、今週もよろしくお願いします!
幹事報告
地区行事等の開催自粛についてのお知らせ
地区補助金プロジェクト申請締め切り延長のお知らせ
委員会報告
お世話になっております。ロータリー米山記念奨学会です。
今月の“ハイライトよねやま”ができあがりましたので、お送りします。
ぜひご覧いただければ幸いです。
何とぞよろしくお願い申し上げます。
▼全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight240_pdf.pdf
(公財)ロータリー米山記念奨学会ニュース
………………………………………………………………………
★ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま 240号 ★ 2020年3月12日発行
………………………………………………………………………
::今月のトピックス::
——————
・2020学年度の選考を全地区で実施
・終了式・オリエンテーションの開催状況
・寄付金速報 ― 新型ウイルスの影響で大幅減 ―
・マレーシア学友会総会 ― 米山の友情を確認 ―
・タイ学友会総会 ― 新役員が決定 ―
《今月のピックアップ記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
終了式・オリエンテーションの開催状況
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルスの感染拡大は、イベント自粛や学校の休校
など、社会に深刻な影響を与えています。ロータリー地区に
おいても例外ではなく、例年2~3月に各地区で開催される米山
奨学生の終了式も今年は中止や縮小を余儀なくされた地区が
多くありました。
現在、当会では、終了式およびオリエンテーションの開催状況
について、各地区にアンケートを実施中です。3月11日現在、
34地区中27地区から回答をいただいており、終了式について
「中止した」という地区は17地区、「予定通り開催した」と
回答した10地区も、「規模を縮小して実施」、「懇親会は
行わず授与式のみ」など、感染予防に最大限配慮した対策が
取られました。
4月上旬から5月にかけて各地区で開催されるオリエンテーション
については、新規奨学生への重要事項の説明の場であることから、
現時点では「予定の日程通り開催する」と回答した地区が多い
ものの、「今後の状況により延期・中止の可能性あり」とする
地区もあり、まだ流動的な状況です。集合型オリエンテーション
の中止を決定し、「地区委員が手分けして電話で説明」、
「奨学会のパワーポイント資料の解説動画をつくり、奨学生には
視聴後に感想文を提出してもらう」などで対応する地区もあります。
過去に経験したことのない困難な状況の中で新学年度がスタート
しますが、米山奨学生たちが「ロータリーと出合って本当に
良かった」と言ってくれるよう、当会としましても、各地区と
連携して万全を期す所存です。何とぞご協力のほど、
よろしくお願いいたします。
そのほかの記事は、ぜひPDF版をご覧ください。
卓 話
インターアクトの環境保全活動
福山太一
先日子供と一緒に本を読んでいると、「海の水はなぜ塩辛いのか」という話が出てきました。その説明は川の水が海に流れ込んでいるからというものでしたが、根っからの文系人間の私にとってはキツネにつままれた気分になるものでした。少し調べてみると、川の水は淡水と呼ばれますが、これは全く塩分が含まれていないわけではありません。元となった雨水には既に様々な大気中の物質が含まれており、それらに加えて川の水は、陸地を流れる間に岩や石にふくまれている塩分を、少しずつとかしこみながら海に流れ込みます。海水は常に蒸発していますので、塩分濃度があがり、川の水は塩辛くないのに、海の水は塩辛くなるということです。
ところで、川が海に運んでいるのは塩分だけではありません。山や森に降った雨は、そこに生える植物の葉や腐葉土の中に蓄えられ、その過程で栄養分が溶け込み、ゆっくりと川や海へと流れ込みます。海では、その栄養は植物プランクトン、海藻などに利用され、食物連鎖により動物プランクトン、魚類などへとつながります。そして、魚類は、漁獲や、遡上、陸上動物による捕食などによって再び陸地に戻ります。したがって、森・川・里・海の絶妙なバランスにより、豊かな生態系は保たれているのです。
私は教員・顧問として滝川中学校・高等学校インターアクトクラブに関わっていますが、かつて活動の際にある漁師さんより“魚つき林”の話を伺ったことがありました。昔から漁師は良い漁場を維持するために地域の森を大事にしてきたのですが、これは経験的に窒素やリン、珪素等の栄養塩の供給源としての豊かな森の重要性を理解して知恵として継承してきたということです。地球の環境は山から海に至るまであらゆるところで密接に関係し合っているということを改めて思い知りました。
この話に触発されたわけではないのですが、気が付けばこの10年ほどの間に、滝川中学校・高等学校インターアクトクラブでは山や森、里、海で様々な活動をするようになっています。
山では、兵庫県で40年に亘り森林ボランティア活動をされているNPO「ブナを植える会」のご指導の下、但馬地方でのブナの植樹・育樹活動並びに六甲山系の里山再生活動をさせて頂いています。ブナは水源涵養力が高く、森の母、緑のダムとも呼ばれます。鉢伏高原の高丸山登山口にはクラブの記念植樹地もあり、私自身毎回訪れるたびにその成長を楽しみにしています。
里では、兵庫県下のインターアクトクラブと協力して、豊岡で無農薬の合鴨農法によるインターアクト米作りを行っています。この取り組みは元々東日本大震災後の復興支援活動の一環として始まりました。震災直後から本校では、東北支援のため「お米の一握り運動」を実施しました。これは、各家庭から少しずつお米の寄付を募り、義捐米として東北でボランティアをした際に仮設住宅にお住まいの方にお渡しするものです。そこから現在は生徒自らがお米を栽培し、支援する活動へと発展したのです。豊岡は一度絶滅したコウノトリと共生する街づくりを進めています。殺虫剤や農薬を使わないことで、コウノトリの餌となる水生生物の生育できる環境を守るとともに、過大なリンや窒素が海に流れ込むのを防ぐことができます。
海では、兵庫県南北の須磨海岸や竹野海岸の漂着物回収・清掃活動の他、宮城県石巻市牡鹿半島の漁村でワカメ漁のお手伝いをしています。この活動も元々は、東日本大震災の復興支援のために開始したものです。この漁村には、2011年の5月にがれき撤去などの復旧作業のボランティアのため訪れたのですが、翌年の春より生活再建のためにワカメ漁のお手伝いをさせていただいています。このワカメ漁支援は実は環境保護活動にもつながっています。森や里から川に流れこむリンや窒素はあらゆる生命に必須な物質ですが、その一方で過大な量が海に流れ込むと、貝毒や赤潮などが発生してしまいます。ところが、ワカメはこの過大な海水のリンや窒素を取り込み浄化する働きがあります。ワカメを700キロ養殖すると、大人2人・子供2人という「ひと家族」が一年間に排出する窒素やリンを浄化することのできるそうです。このように、ワカメ漁は被災地支援と環境保全につながる活動として継続しています。
これらの活動に加え、近年は地域の方々に、環境問題をはじめ、さまざまな社会問題に関心を持っていただくために、ワカメせんべいの開発、インターアクト米ポン菓子の作成、神戸の地域アイドルであるKoberries♪とコラボレーションしたアクトレンジャーショー等も積極的に行っています。
これまでの活動を改めて振り返ると、いつの間にか環境に関わる活動を多く行なってきた事に気がつかせられました。日本では深刻な健康被害を引き起こす公害などが減少したため、ついつい環境問題は見逃されがちですが、マイクロプラスティックやいかなごの減少など身近なところに環境に関わる課題はまだまだたくさんあります。
ところで、インターアクトを支援する国際ロータリーの究極の目標は、「久遠の平和」です。平和を構成する必須の要素はいくつかありますが、その一つが生命の安全であり、その生命を育むものは豊かな自然環境であると私は考えています。今月は「水と衛生」月間ですが、ロータリーは2030年までに、安全な水と衛生設備をすべての人が利用できるように目標を掲げています。この実現のためには、先進国や途上国がそれぞれの立場において、直接間接に自然環境の維持・改善に向けて努力をしなければなりませんし、そのような試みは国連のSDGs(持続可能な開発目標)にも合致するものです。中高生のインターアクトの生徒が出来ることは限られていますが、私はインターアクトの活動を通じて、微力ながら久遠の平和につながる環境に関わる活動を継続していきたいと考えています。
おわりの点鐘
この例会に共感された方は、「いいね」をお願い致します。